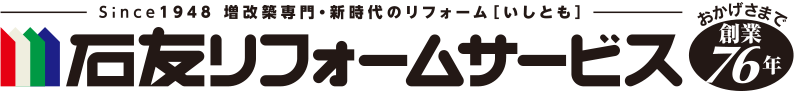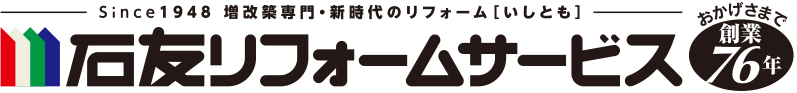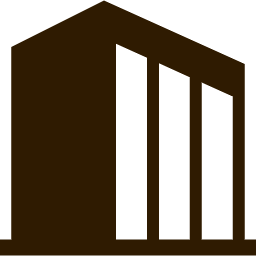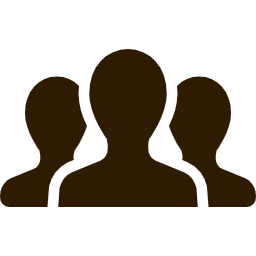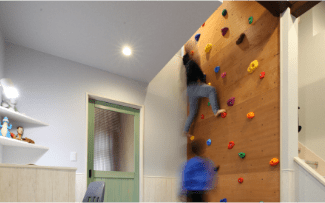*開放感のある折り上げ天井 / 石川県金沢市
https://www.ishitomo-reform.co.jp/renovation/case/details_142.html
地震大国である日本では、いつ大きな地震が起きてもおかしくありません。近年では能登半島地震や熊本地震など、震度7クラスの地震が発生していて、住宅の耐震性への関心が高まっています。
とくに築年数が経過した戸建て住宅に住んでいる方は、「自分の家は大地震に耐えられるのかな」と不安を感じることもあるのではないでしょうか。実際、1981年以前に建てられた住宅は旧耐震基準で建築されているため、現在の基準と比べると耐震性能が劣る可能性があります。
本記事では、戸建て住宅の耐震性能の基本的なことから、耐震補強リフォームが必要な住宅の特徴、具体的な補強方法、そして信頼できる業者の選び方まで解説します。
自宅の耐震性に不安がある方は、ぜひ参考にしてください。
戸建ての耐震性能の種類
戸建て住宅の耐震性能を理解するには、「耐震基準」と「耐震等級」という2つの指標を知っておく必要があります。2つの指標は、建物がどの程度の地震に耐えられるかを表すもので、住宅の安全性を判断する重要な基準です。
それではさっそく見ていきましょう。
旧耐震基準と新耐震基準

耐震基準 / 施工時期 / 想定する地震 / 主な特徴
旧耐震基準 / 1950年~1981年5月31日まで / 震度5程度 / 中規模地震で倒壊しないこと が 目標
新耐震基準 / 1981年6月1日~2000年5月31日まで / 震度5強~震度7程度 / 大規模地震 でも倒壊しない
日本の建築基準法における耐震基準は、大規模地震が発生するたびに見直されてきました。なかでも大きな転換点となったのが、1981年6月1日の建築基準法改正です。
旧耐震基準は1950年から1981年5月31日まで適用されていた基準で、震度5程度の中規模地震で倒壊しないことを目標としていました。しかし震度6以上の大規模地震は想定されておらず、1978年の宮城県沖地震で多くの建物が倒壊したことから、基準の見直しが行われました。
新耐震基準は1981年6月1日から施行され、地震への対策が2つの段階で考えられるようになりました。まず震度5強程度の中規模地震では建物にほとんど損傷が生じないこと、そして震度6強から7の大規模地震でも倒壊・崩壊しないようにするという2つの目標を設定したのです。
なお、2000年6月1日には、さらに改正が行われました。1995年の阪神・淡路大震災で柱の引き抜けや壁の偏りによる被害が多発したことを踏まえての改正です。
実際、2016年の熊本地震では、旧耐震基準の木造住宅の約28%が倒壊・大破したのに対し、新耐震基準では約9%、2000年での改正基準では約2%という結果が出ています。
耐震等級(等級1、等級2、等級3)

耐震等級 / 耐震性能 / 建物の例 / 地震保険割引率
等級1 / 建築基準法の最低基準 / 一般的な住宅 / 10%
等級2 / 等級1の1.25倍 / 長期優良住宅、学校、病院 / 30%
等級3 / 等級1の1.5倍 / 消防署、警察署 / 50%
耐震等級は、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により定められた、住宅の耐震性能を示す指標です。建築基準法で定める最低限の耐震性能を等級1とし、それ以上の性能を等級2、等級3として3段階で評価します。
耐震等級1は、震度6強から7程度の地震で倒壊・崩壊しない、震度5程度では損傷しない程度の性能です。人の命を守ることが目的で、大地震後も住み続けられることを保証するものではありません。
耐震等級2は等級1の1.25倍の地震力に耐えられる性能で、長期優良住宅の認定基準となっています。学校や病院など災害時の避難所は等級2以上が必須です。大地震後も軽い補修で住み続けられる可能性が高く、地震保険料も30%割引されます。
耐震等級3は等級1の1.5倍の地震力に耐えられる最高レベルの性能です。消防署や警察署など災害拠点施設の多くがこの等級で建設されています。2016年の熊本地震では震度7が2回発生しましたが、耐震等級3の木造住宅の倒壊はゼロでした。地震保険料が50%割引となるうえ、大地震後も住み続けられる可能性が3つの等級のなかで最も高いです。
戸建ての耐震補強リフォームとは
戸建ての耐震補強リフォームとは、今ある住宅を地震に強くするための工事のことです。建物の弱い部分を補強して、大きな地震が来ても倒れにくくします。
主な補強工事は以下の5つです。
• 壁の補強:地震の横揺れに強い「耐力壁」を増やしたり、壁の中に斜めの木材(筋交い)を入れて補強したりする
• 基礎の補強:コンクリートのひび割れを直し、基礎と土台を金具で固定する
• 接合部の補強:柱と梁などのつなぎ目を金具で強化する
• 屋根の軽量化:重い瓦屋根を軽い金属屋根に変えて、揺れを小さくする
• 劣化部分の修理:シロアリ被害や腐った木材を交換し、雨漏りを直す
シロアリに食べられた木材や腐った部分があれば、新しいものに交換が必要です。また、雨漏りも木材を腐らせる原因になるので、きちんと直すことが大切になります。
耐震補強リフォームをするべき戸建ての特徴
耐震補強リフォームが必要かどうかは、下記のようなポイントから判断できます。
• 建築年
• 建物の形や構造
• 建物の傷み具合
• 立地
• 過去の被害の有無
現行の基準よりも前に建てられた戸建ての住宅は、耐震性能が劣っている可能性が高いため、耐震補強のリフォームがおすすめされます。
建物の形や構造も大切なポイントです。1階に大きなリビングがあって壁が少ない家、南側に大きな窓がたくさんある家、車庫がある家は要注意です。L字型やコの字型の家、大きな吹き抜けがある家なども地震に弱い傾向があります。
建物の傷み具合では、基礎や外壁のひび割れ、ドアや窓の建て付け不良、雨漏りの跡があれば早めの対策が必要です。
土地の条件も大切で、埋め立て地や川の近く、地盤が弱い土地では揺れが大きくなります。
また、過去に地震や台風で被害を受けたことがある家は、見た目は大丈夫でも、見えないところにダメージが残っているかもしれないため、耐震診断を行い、必要に応じて耐震補強リフォームの実施をおすすめします。
判断が難しい場合は耐震診断を受けるのもおすすめ

戸建て住宅において、耐震補強リフォームすべきポイントが分かっても、実際に自宅に必要かどうかを一般の方が判断するのは難しいでしょう。そのため、専門家による耐震診断を受けることを強くおすすめします。
耐震診断では、建築士や耐震診断資格者などの専門家が、建物の構造や劣化状況を詳しく調査します。診断結果は以下のように「総合評点」として示されます。
総合評点
1.5以上 倒壊しない
1.0~1.5未満 一応倒壊しない
0.7~1.0未満 倒壊する可能性がある
0.7未満 倒壊する可能性が高い
総合評点が1.0未満の場合は、耐震補強が必要と判断されます。耐震診断の費用ですが、自治体によっては耐震診断の補助制度があるため、まずは自治体の窓口に相談してみるとよいでしょう。
戸建ての耐震補強リフォームの流れ
耐震補強リフォームは、以下の7つのステップで進めます。
1. 事前相談・情報収集
2. 耐震診断の実施
3. 補強計画の立案
4. 見積もり・契約
5. 補強工事の実施
6. 完了検査・引き渡し
7. アフターフォロー
まず複数の業者に相談して、費用の目安を把握しましょう。役所などで補助金制度も調べておくとよいでしょう。
次に専門家による耐震診断を受けます。家の中や外、床下や屋根裏まで調べてもらい、どこが弱いかを点数で評価します。診断結果が1.0未満なら補強が必要です。
診断結果をもとに、どこをどのように補強するかの計画を立て、見積もりを出してもらいましょう。内容と金額に納得できたら契約し、耐震補強リフォームを実施します。
また、リフォームが終わったらそれで終わりではなく、耐震性能を保つために定期的な点検を行ってもらうことが大切です。
戸建ての耐震補強リフォームを依頼するときの業者の選び方
戸建ての耐震補強リフォームの成功は、信頼できる業者選びにかかっています。そこで、業者の選び方をご紹介します。
耐震補強リフォームに関する資格を保有している業者を選ぶ

戸建ての耐震補強リフォームには専門知識が必要なため、以下のような資格を持つ人がいる業者を選びましょう。
• 耐震診断資格者:木造住宅の耐震診断の専門資格
• 耐震技術認定者:耐震診断や補強の専門技術者
• 建築士(一級・二級):建築全般の国家資格
• 建築施工管理技士:工事管理の国家資格
• 既存住宅状況調査技術者:建物の劣化診断の資格
一定の実務経験がなければ取れない資格もあるため、上記の資格を持つ人がいる業者であれば安心して依頼できるでしょう。
戸建ての耐震補強リフォームの実績が豊富な業者を選ぶ

実績が豊富な業者は、いろいろな家の状況に対応できる経験があるので安心です。実績の豊富さを判断するには、以下のポイントを確認しましょう。
• ホームページやパンフレットで実際の工事例を公開している
• 自分の家と似た築年数や構造の施工実績がある
• 複数のプランを提案してくれる
• 各プランのメリット・デメリットを説明してもらえる
まとめ
地震はいつ起こるか分かりません。とくに1981年以前に建てられた住宅や、築年数が経って傷みが目立つ住宅に住んでいる方は、早めに耐震診断を受けることをおすすめします。
耐震補強リフォームは費用がかかりますが、命を守るための大切な投資です。自治体によっては補助金制度もあるので、うまく活用しながら進めていきましょう。
まずは複数の業者に相談して、自分の家にどんな補強が必要か、費用はどのくらいかかるのかを把握することから始めてみてください。資格を持った専門家がいて、実績が豊富な業者を選ぶことが成功のカギです。
石友リフォームサービスでは、富山・石川・福井・埼玉エリアで多くの耐震補強リフォームを手がけてきました。経験豊富なスタッフが、住まいに最適なリフォームをご提案します。
戸建ての耐震補強リフォームを検討している方は、ぜひ石友リフォームサービスにご依頼ください。
石友リフォームサービス 富山エリアの情報はコチラ
石友リフォームサービス 石川エリアの情報はコチラ
石友リフォームサービス 福井エリアの情報はコチラ
石友リフォームサービス 埼玉エリアの情報はコチラ
 0120-64-0300
0120-64-0300